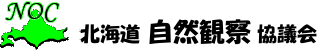2024年6月の行事一覧
「新川〜オタネ浜」観察会
| 開催日 | 2024年06月22日(土) |
|---|---|
| 観察地 | 新川〜オタネ浜 |
| テーマ | |
|
一般参加者4人、指導員2人の計6人でスタート。曇りから晴れに変わり暑いくらい。 海まで続く白く乾いた砂利道の両側の自然観察から始める。ここには、他の道と同様、イタドリが繁茂していたが、それらが無いところには外来植物が目立った。タンポポモドキ(ブタナ)から始まって、シナガワハギ、レッドクローバ、ホワイトクローバ、ムラサキウマゴヤシ、ヘラオオバコ、フランスギク、オニハマダイコンなどの植物をはじめ、ニセアカシア、イタチハギなどの樹木も紹介された。 これらの中で、シナガワハギ、ムラサキウマゴヤシなどは、詰め草として利用されていたと紹介されると興味深く参加者たちは聞き入っていた。またこれら外来植物に関わって、オオイタドリがイギリス等の国々において日本から持ち込まれて、その繁殖力の旺盛さから相当はびこってしまい、この植物があると不動産価値が下がるという問題をも引き起こしていることも伝えられた。また木の葉の黄ばんだものを利用して道内に棲息するコウモリがいると聞かされて皆一同、ビックリ。 新川に沿って河口に向かったので、指導員から同川の建設経過とか、河口にあったオタルナイ場所の運上屋とか、海岸線と柏の純林の中を通る銭函から石狩まで続く道がそれぞれあったこと、また明治半ばに山口地区を襲ったトノサマバッタの卵とか死骸を集めて塚を作ったバッタ塚(札幌市の文化財)などの新川河口にまつわる様々な歴史も伝えられた。 オタネ浜については、海側から陸に向かって渚、砂浜、砂丘、後背池、後背林というように帯状にゾーンが分けられ、それらに照応した様々な生き物、植生があるという意味で非常に、今日、貴重な自然海岸であることが紹介された。 特にこれらのゾーンの中でメインの砂丘地帯では、ハマニンニク、ハマエンドウ、ハマナス、ハマヒルガオなどのハマという名が付いた植物が、地中深く根を張って砂の飛散を防いでいる状況を実際に観察した。 またこれら海浜植物と言われる植物が、近年の風車建設に関わって、国道から一般車の乗り入れ禁止が続けられてきた結果、バギー車等による踏みつけ等が無くなったため、かなり復活していることを確認した。 雨にも当たらず、少数精鋭の人数であったが、参加者、それなりに得るものもあったようで、また次回にも参加したいという人もいた。 (札幌市手稲区 村元健治) |
|
 シロバナシナガワハギ |
 ハマナス |
 ハマボウフウ |
 オタネ浜 |
2024年6月22日